
こんにちは!ともや先生です!
ゲームとの付き合い方って難しいですよねぇ~
今はほとんどやらなくなりましたが、僕も昔はどっぷりゲームにハマッておりました。
なのでゲームにのめりこんでしまう子ども達の気持ちもわかるような気がします。
そこで親として気になるのは「子どもとゲームの付き合い方」ですよね?
最初に知っておいて欲しい事
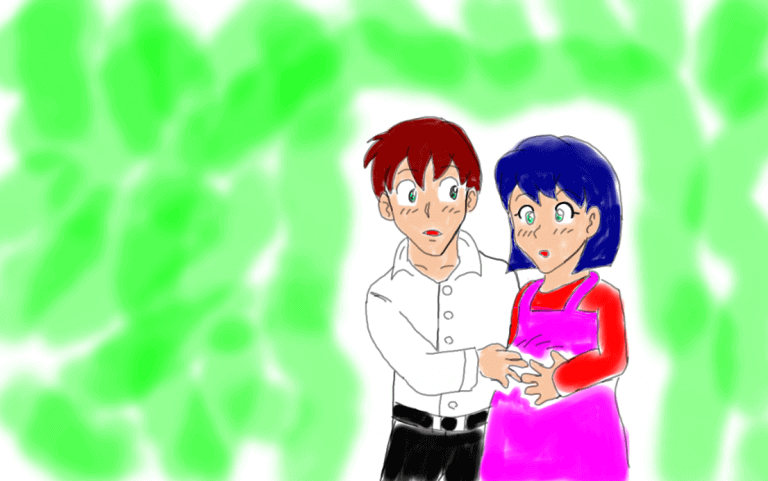
無理に引き離そうとせず、まずは理解を
1度ゲームの楽しさを知ってしまったが最後!子どもはあの手この手でゲームをやろうとします。
無理に制限しようものなら、親の目の届かないところでやろうと企てるハズです。
ですが、子どもが親の思い通りにならないのは至って普通の事。なんでも大人の言うとおりになる方が心配です。
そこで、まず親のすべきことは、ゲームに対して正しい理解をするということです。メリット・デメリットを知って、それから考えていきましょう。

確かに今までゲームをあまりやてこなかったような人にとっては、ゲームがどんなものかよくわかっていないですよね。

僕自身、隙あらば親の目を盗んでゲームをしていた少年の一人ですので、子どもがゲームをしたい!という気持ちは痛いほどよくわかります。
どうしてもゲームをやらせたくないなら初めから与えない
元も子もない話ですが、本当にゲームをさせたくないなら、初めからゲームを与えない事です。楽しみを知った上で制限されるのはかなり苦痛だったりします。
楽しみを与えてから奪うのは、子どもも絶望してしまいます。
上記もしましたが、親もゲームに対する理解がある。という事を示す事が大切です。

大人でも今更「スマホ禁止!」なんて言われたら受け入れられませんよね。

ホントです!私でも「インスタ禁止!」なんて言われたら無理です!
ゲームの良いところ4
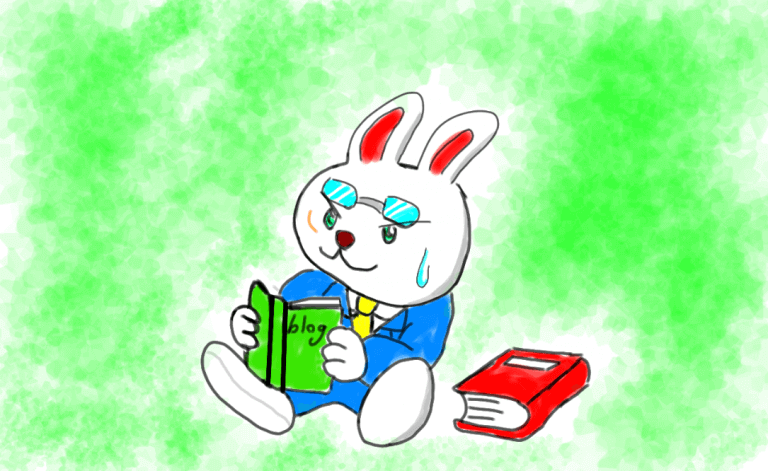
ゲーム否定派の方達も、一方的に否定するのではなく、まずはメリットとデメリットを正しく理解する事から始めてはいかがでしょうか?
以下がゲームから得られるメリットです。
- コミュニケーションツールとして有能
- 思考力がつく
- 楽しく勉強できる
- お金がかからない

皆さんも1度はゲームにはまった経験があるのではないでしょうか?
ゲームは今、昔よりもだいぶ進化しています。
①コミュニケーションツールとして有能
「親子の触れあい」や「友達同士」でコミュニケーションが深められます!
まずは「親子の触れあい」についてです。
ゲームに限った話ではないのですが親と一緒に夢中になって同じモノに取り組む!というのがなによりいいんです。

同じ土俵で「親と肩を並べて競い合う!」子どもがワクワクしないハズがありませんね!
そして「友達について」です!
昔と違って今は家にいながらオンラインで友達とも繋がれるのでコミュニケーションツールとしても、おおいに活用できるのです。

昔はゲームは一人でやるもの。なイメージが強かったですが、今は一人でもいろんな人と繋がれます。会話もできます。
ゲームを始めた頃に最初だけ、僕も父親とゲームをした記憶があります。
確か「タートルズの格ゲー」だったと思いますが、すっごく嬉しくて楽しかったです。
父親は忙しく、あまりゲームはできませんでしたが、一緒にやった記憶は今でもよく覚えていますよ。
友達も「父親とポケモンの対戦をしている。」と嬉しそうに語っていました。
②考える力がつく
「You Tubeよりは全然いい!」という意見もある程です。

確かに、動画はただ見るだけなので「受け身」ですが、ゲームは自分で考えて進めなくてはいけませんね!
ゲームの内容にもよりますが、いろいろと試行錯誤して取り組むのは良いことだと思います。
例えば以下のような事…
- ゲームクリアの為に頭を使う
- 制限時間内に条件を満たすには?
- このアイテムを買うためにはあといくら必要?
- キャラの相性を計算してパーティー編成!
- 現実のお金で課金してみる?
ただなにも考えずにプレイしてクリアできるほどゲームは甘いものではありません。

戦わせるキャラ同士で相性があったり、ボスの動きのパターンを分析したり、何回も負けながら挑戦したり、地道にモンスターを倒してお金稼ぎをしたり…
③楽しく勉強できる
小さいウチは「勉強」と「遊び」の境目はないのです。親としては「ゲームと学びをうまく結びつけられる」事ができれば嬉しいのではないでしょうか?
ゲームから学ぶものもたくさんあります。
ゲームからキャラクターが話している言葉を理解して、言葉や漢字を覚える事もあります。
学校では教えてもらえないような事や、アプリから、インターネットとというもの、ネットの世界への理解を深める事もできるかもしれません。

実際に僕の息子もタブレットアプリで平仮名の書き順や漢字、英単語や九九も覚えています。
他には歴史物のゲームの場合、様々な事を疑似体験できたりするんです。
アニメを見るのとは違い、キャラクターを自由に動かせるので、より仮想空間に没入する感覚が味わえます。

僕の場合は「武者ガンダム」や「鬼武者」で歴史に理解を深めました。友達だと「信長の野望」とか好んでプレイしていましたよ。
昔は考えられませんでしたが、今では「お小遣いでゲームに課金する。」ということも一般的になっていると言われています。
お金の勉強もゲームを通じてできる場合があります。
④お金がかからない
このメリットは思いっきり大人視点ですね。あまり言いたくないですが、お金も大切です。
昔はゲームソフト一本に一万円近くかかったりしていましたが、スマホ・タブレットであれば無料でダウンロードできるゲームはいくつもあります。
今の時代、無料のスマホゲームは非常に優秀です。
- 将棋やオセロのようなボードゲーム
- テトリス等のパズルゲーム
- 障害物を避けて進むランゲーム
- 足し算やかけ算をする算数ゲーム
- 英語や平仮名を楽しく楽しく学べるゲーム
探せばいくらでも出てきます。
個人的にはオフラインで出来るゲームが好ましいと思います。
ネットに繋げなくてもプレイできますしね!勝手にいろんなゲームをダウンロードされちゃうと大変なことになるかもしれません。

僕自身「無課金でどれだけ強くなれるか!?」なんて挑戦したりしていました。「パズドラ」のようなパズルゲーム。「ヘイデイ」のような農場ゲーム。「クラッシュ・オブ・クラン」のような戦術ゲームにもはまりました。が、全て無課金でやってました。
ゲームのよくないところ3
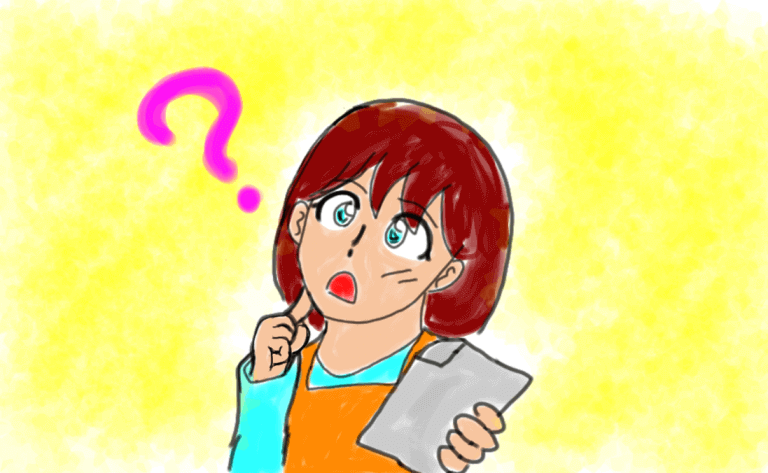
良い部分はどんどん伸ばせばいいと思います。
問題なのは「そうでない部分」ですよね?
①他の事がおろそかになる
おそらく個人的に1番困るのはこの部分なのではないでしょうか?
ゲームがダメなのではなく、問題なのは「ゲームばかりで他の事がおろそかになってしまうこと。」
シンプルですが、親としてもこれが1番困るのでは?
あくまで、依存症になるほどのやり込みはNG。
- ゲームばかりやってご飯食べない!
- ゲームに熱中して就寝時間を守らない!
- 朝起きたらすぐにゲームやりたい!
ですがこれはデメリットの反面やり方次第では良い方にも傾けることが可能だと考えます。

ゲームを楽しみに他のこと頑張れる!というのは大人でもいるのではないでしょうか?
②目が悪くなる?
ゲームのデメリット
ゲームのデメリットとして昔からよく言われているのは「目が悪くなる!」というものです
確かにそれはその通りなのですが、目が悪くなるという構造は近くのものを長時間ずっと見続けているということで起こります
しかしこれはゲームに限った話ではありません
- ずっと本を見続けている
- ずっと勉強をしている
- ワーク等ずっとやっている
解決策としては簡単です!「外遊び」です
外に行けば目が良くなると思ってくれて構いません午前中はお家で過ごして午後は外遊びをしてもいいかもしれません2時間は外に出たいところです
③睡眠の質が下がる
これも昔から言われていることです。
※これにはメラトニンという物質が関わってくるのですが、話し出したらキリがないので割愛しておきます。
寝る前は控えておきたいところです。
ちなみに我が家ではお風呂入ったあとはゲームはやらないと言うようにしています。
それでもやりたいやりたいとなることがありますが、その時の対処法は後述いたします。
今すぐ知りたい人はコチラ
NG行動
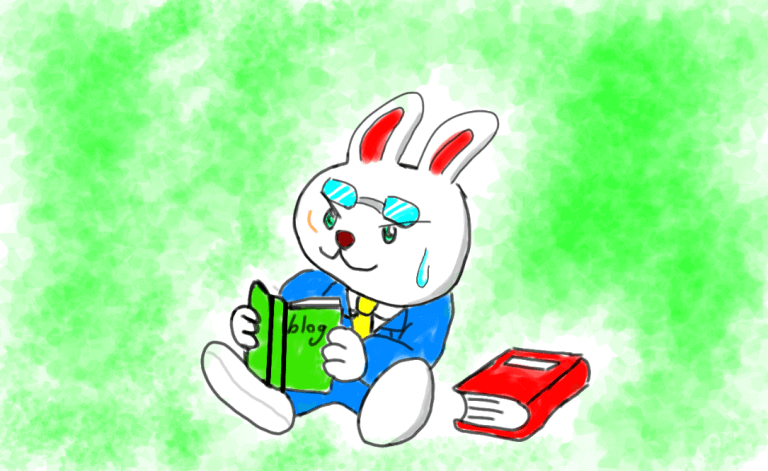
まずは絶対にやってはいけないことのお話しをします。
ゲームを悪者だと決めつけない
よく知りもしないのに、イメージだけで横からゴチャゴチャ言われても、うっとおしかったりしますよね。
学校でも「テレビやゲームの時間を決めましょう」というような内容のプリントをいただく事があります。
ですが、読書や勉強は何時間でも良くて、テレビやゲームはダメなのはなぜでしょうか?実際に子どもに聞かれた場合、うまく説明できますか?
ゲームを一方的に悪者と決めつけるのは誤りです。
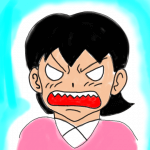
ゲームをするとバカになる!!!
昔はまだ、そのような考えが根強かったですが、今はだいぶ変わってきています。
この認識は、はっきり言って時代遅れという他ありません。

自分の好きなモノに対し、自分の好きな人の理解を得られないって悲しいですよね・・・
自分の好きなモノを、大好きなお父さんお母さんに否定される事ほど、子どもにとって辛いことはありません。

ゲームって楽しいよね!私も大好き!
まずは理解を示すことが何より大切です。
制限されてしまうと、余計やりたくなってしまうものです。僕自身そうでした。
ゲームに限らず、自分が好きなもの、楽しいと思っている事を否定されてしまうと自分自身を否定された気分になってしまいますね。
無理矢理子どもの行動を制限してしまうと、子どもは親の目の届かないところでやるようになります。
一番多いのが頻繁に友達の家に入り浸る。
僕にも経験ありました。
やっていたのはRPG。まだセーブポイントまでたどりつかないうちに、タイマーが鳴ったから唐突に終了を宣言された時は絶望しました。
その頃の僕は、親に対して「ゲームというものをまったくわかっていないんだな。」と絶望したものです。
「セーブポイントまでいってないから、今やめるとまた最初からやりなおしになる。」といくら訴えても「時間だから!」と押し切られ、怒られ、無理矢理辞めさせられました。
その反動で、友達の家でゲームをするようになりました。友達の家ではいくらやっても怒られなかったからです。
僕が子どもの頃、ゲームは1日30分と言われました。
特にRPGなんて、30分だけだとレベル上げだけで何日も何週間も費やす事となります。
衝撃的だったのは「たまごっち」をいじる時間ですら、1日の30分の中に組み込むというものでした。
子ども心に「親はゲームの事をなにもわかっていないんだな。そんなこと言うなら初めから買わなければよかったのに。」と思ったものです。
無理矢理ゲームを奪う
強制的に子どもとゲームを切り離そうとすることは逆効果です。
「見るな」と言われたらますます見たくなり、「秘密」にされるとますます知りたくなるのは普通の事。

僕も昔はゲーム機を親に隠され、家中探し回ったのを覚えています。
無闇に禁止したり、とりあげたりすると後で反動がきたりするものです。
なので、無理やり引き離したところで根本的な解決にはなりえないのです。
取り上げるのであれば、最初から与えないのが1番いいですね。
これは1つの例ですが、
やることはやり終えてからという条件で、最長で2時間くらい。あまり取り上げすぎて執着心が強くなるのも怖いし、小学生ともなると男女問わず遊びの選択にゲームはどうしてもあって、その時に話や遊びについていけなかったら大変かなあとも思います。
というような意見も見られます。
自分からやめられるようになる方法6
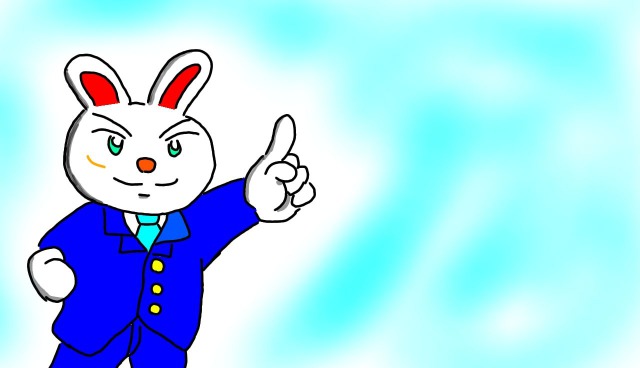
上記もしましたが、親としては「依存してしまうこと」がなにより心配なんですね。
なので、僕も実践する方法を交え、お伝えしたいと思います。
僕自身、小さい頃はゲームの時間を守ることができず、怒られる日々でした。
①まずは親がスマホをやめる
そもそも大人は空いた時間にスマホを見てるのに、子どもに対してだけ制限を設けるのはおかしいのです。

これは仕事のラインを返してるの!!
本当だとしても、そんな理屈は子どもに通じません。
スマホを見ている時点でそれは「ゲームをしている」と思われるのは当然のことだと思います。
やるのであれば、子どもに見えないように行いましょう。

僕は子どもの前では本を読むようにしています。「恐竜大百科」とか、自分も子どもも楽しめるような本です。スマホは時間を守って使うようにしたいのは大人も子どもも一緒ですね。
②自分からゲームをやめたくなる場合もある
まず、大好きなゲームであってもやりたくない時だってあります。
「好きな事は仕事にしちゃいけない。」「仕事にすると嫌いになる。」なんて話は聞いたことあるでしょうか?
好きな事であっても、他人から強制されると嫌になってしまう場合があります。
趣味とは、自分の好きな時に好きなだけやれるから楽しいんです。

「趣味」ではなく「作業」になってしまいまうんですね。
知人の話です
ある日、何度やっても倒せないボス戦を見ていた母が、「クリアするまでゲームやめちゃだめ!」と言ったそうで、泣きながらゲームをやったことが過去にあったそうです。
③プレイする時間は自分で決める
最初に「どれくらいやるか」子ども自身に聞いて、自分で決めてもらいましょう。
そこでこんな事を言われるかもしれません。
実際に僕と息子のやり取りを例に挙げます

タブレット、今から何分やる?

500ぷん!!!
ちょっと待て!!!!!と思いました。
ここで「それはムリ!!」と言うのを一旦飲み込みましょう。

なるほど、500分か。悪くないけど、そんなにやったら朝になっちゃうなぁ…寝る時間なくなっちゃうかもしれないよ?15分でもいい?
子どもの意見は否定せず、一旦受け止め、説明し、新たな提案をしてみました。

わかったー。
と言ってすんなり受け入れてくれました。
年齢にもよりますが、ある程度ルールを作っておくことも重要です。
ですが、あまりに細かく指定しすぎるのはNG。
僕はやることが全て終わってから!というように伝えています。
④やめる時は一緒に参加
ゲーム機のタイマーは効果なし。というのは聞いた事ある人はいるのではないでしょうか?
楽しんでいる最中にいきなり終了してしまうわけです。そんなの納得いくはずがありません。
そもそもゲームをする人が、やめる時間も決めるのは当然のことではないでしょうか?
個人的にですが、やめる時は「一緒に参加する。」が1番効果的に感じます。
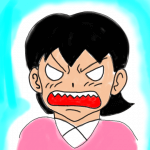
いつまでやってんの!いい加減にしなさい!
と言って素直にやめてもらえるはずがありません。

やだー!!!もっとやるーーー!!!!
という反応が返ってくるのは普通の反応です。
例えばですが、大人でもカラオケで気持ちよく歌っている最中に「時間だから」という理由で強制的に電源を落とされ強制終了されたとすると、どうでしょうか?そこに不満が残ってしまうのではないでしょうか?せめて、今流れているこの曲だけは歌わせて欲しい!と思うのではないでしょうか。
可能であれば、最初から一緒にゲームに参加してみるといいでしょう。それが難しい場合は、途中からでもかまいません。

ゲームをやっている隙に様々な舵をこなしたい場合もあることでしょう。
タイマーをセットしてもいいのですが、時間になったら「なにをやっておしまいにする?」「今やってるのが終わったら片付けようか」等提案し、子ども自身に終わるタイミングを決めてもらうのが1番いいと思います。

お!いいね!上手だね!次はなにがくるのかな?
あ、もう時間だ!今やってるのクリアしたら、また明日にしようか?
年齢にもよるかもしれませんが、実際に我が子に対してもそうでした。
当時タブレットで文字を書くアプリに大ハマリです。
その間に家事をこなします。
※その場合も聞こえてくる情報に対して反応し声をかけるようにしています。
子どもからしても、大人がゲームに対して理解がある。と思うと嬉しいものですよね。
時間を見て、そろそろかな?と思ったタイミングで側に座り、一緒に楽しみます。
「もうそろそろ時間だね!最後になにやる?」
「1から20まで書いたらおしまいにする!」
それくらいなら5分もかかりません。
「20」まで書いた息子はタブレットをとじて、自分から片付けてくれました。
「ゲームや動画の時間を0にする」ことよりも、「バランスを取ること」「ほどよい着地点を見つける」ということを子どもに教えていくこともまた、難しいことではありますが、親ができる教育のひとつではないでしょうか。
⑤【大事】ゲーム以外の楽しみを用意する
そもそも、子どもはなぜゲームにハマってしまうのでしょうか?
言葉にすると簡単です。
それは「ゲームが楽しいから」もっと言うと「ゲーム以上に楽しい事が見つからないから」です。
なので解決策は単純です。 別の楽しみを用意すること。ですね。

人は楽しみが1つだと、それに依存しやすくなってしまいます。
マンガ本など、ちょっと没頭できて、子どもが楽しめる何かを準備しましょう。
「動画より面白い!」と感じられれば、子どもの興味はそちらに移り、夢中になっているうちに、ゲームや動画の時間が結果として減ります。
大人なら自分で他の楽しい物を見つけられますが、子どもはまだ視野が狭いので、親がゲーム以外の物に触れさせる機会を作ってあげるのが1番いいと思います。
個人的に1番オススメしたいのは、家族で出掛けてしまうことです。
遊園地とかでなくてもいいんです。
近所の公園でもいいんです。親と一緒にお出かけするということは、子どもにとってなにより嬉しいんです。

行ったら行ったで公園が楽しくてなかなか帰ってくれなかったりします。
キッカケを提供すれば、子どもは自分で遊びを見つけます。
他にはボードゲーム等を広げて待機!というのもいいと思います。
僕はオセロとか準備して横で待ってたりしますよ。
対人でしかできないものって、楽しいですよね!
⑥とことんやらせる
後述しますが、僕はゲーム大好きっ子だったのにも関わらずゲームをやらなくなりました。
それはゲームをやりまくった事にも一因があるのではないか?と思います。
さんざんやったから気付いたものもあるのでしょうか?
- 純粋に「飽きた」
- お腹いっぱい
- どういうものなのか理解した
ということでしょうか?
少なくとも僕は、誰かに強制されることもなく自然と自分からゲームを手放しました。
詳しくはコチラ
まとめ

極端に制限するのは逆効果。
好奇心を煽って、さらにゲームにのめり込んでしまう。
よく知りもしないで「ゲームは悪者!」だと決めつけて制限するのはいかがなものかと。
親でしたら、ゲームすらも味方につけてしまいましょう!!
肝心なのは、終わりのタイミングは子どもに決めさせる。終わった後になにをするかを明確にする。ゲーム以外の楽しみを用意する。です。
個人的には、あえてのめりこませる。というのも有効かと思います。





コメント