
こんにちは!ともや先生です!
保育園にもマニュアルって必要?不要?
今回は保育園における「マニュアルの大切さ」についてお話しさせていただきます。
特に「管理職の方には知っておいて欲しい!」ということを書いたつもりです。
是非、目次から「知りたいところだけ」でも見ていって下さい。
マニュアルってどんなもの?
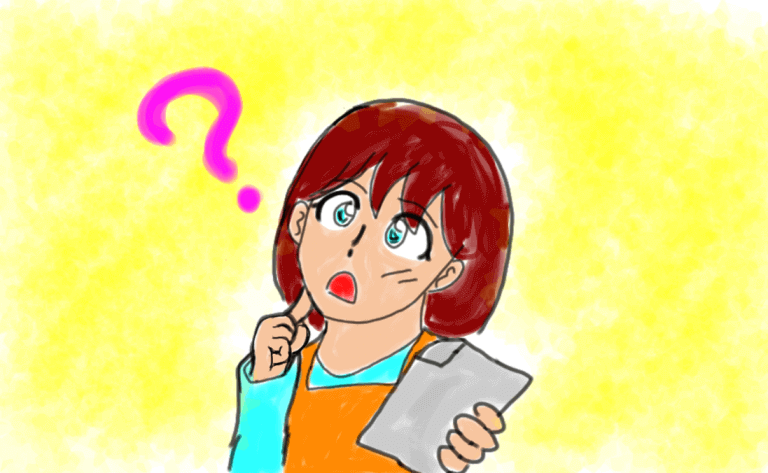
僕も最初はこう思ってました…
- マニュアルなんて役に立たない
- 読んでも意味ない
- 読んでもなんかよくわかんない
- 現場で覚えるしかない
- ただ棚にしまわれているだけの書類
- 誰も見ない

こんなイメージでしたが、大いなる勘違いでした。
管理職に就いてから思う事です。
マニュアルの事について勉強してみると、全く認識が変わりました。
【誤解】現場の「気付き」を集めて、日々「更新」していくもの
よく勘違いされがちなのがコレです。
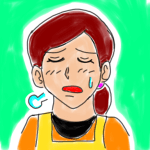
これはこう決まってるんでこうして下さい!余計なことはしないで、決まったことだけやればいいの!
先生を型にはめて、ロボットにしたいワケではありません。
現場には日々たくさんの気付きがあります。それを集めて、みんなで共有して保育の質を上げていく為のモノなのです。

「マニュアル」と聞くと、ちょっとお堅いイメージかもしれませんが、そんなことないです。
マニュアルというものは…
- やってみたらこうだった
- これが大変だった
- こんな間違いがあった
- こうした方がいいのでは?
みんなの気付きを集め、どんどん更新して共有するものです。
「言った」「聞いてない」を防ぐ
マニュアルがなく、個人の勘や経験に頼ってしまうと必ずと言っていいほど、こんな事が起きます…
- 言った
- 言わない
- 言ったはず
- 聞いてない
- 知らなかった
- そうでしたっけ?
- いつ変わったんですか?

ぼく自身も、何度もこのような光景を見てきました。「言った・聞いてない」で揉めるのは本当に不毛です。
口伝えだと曖昧になってしまう場合があります。
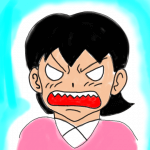
いつもこうやってる!
去年はこうだった!
私はこうだと思ってる!
人間の記憶なんてけっこう当てにならないことが多いんですよね。
このようなトラブルも、きちんとしたマニュアルがあれば一発で解決するハズです。
純粋に教える方も楽になるんです。ちゃんとしたマニュアルがあれば…

ここに書いてありますので、わからなくなっちゃったら自分で確認してみて下さい。それでもわからなかったら、いつでもいいので聞いて下さいね。
教える方もかなり手間が省けます。
後になってから…

えー!?言ったハズなんだけどな…
なんて思っても意味がありません。
証明のしようのない事で揉めるのは本当にムダです。
〇〇先生がいないとわからない!を防ぐ
特定の一人の先生に依存してしまうと保育園自体が個人に左右されてしまう場合があります。
経験を積んだ先生が辞めちゃうと誰もやり方がわからない!いうのは組織として好ましくありません。

いつ誰が突然に辞めても大丈夫!なようにする為にマニュアルがあります。
新人でもマニュアルを見てある程度自分で動けるようになるのが好ましいですね。
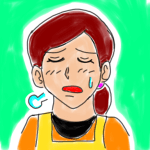
まさか辞めるとは思ってなかった…
なんて言っても「後の祭り」です。
これを「属人化」というそうです。業務がブラックボックス化してしまっては、管理する側も大変です。
人によって「やり方がちがう!」をなくす
こんな経験ありませんか?

〇〇先生の言われたとおりにやったら、××先生に違うと指摘された!一体どうすればいいのー!?
これでは混乱してしまいますよね。
マニュアルは、職員間で「やってる事が違う」という事をなくす為にも一役買います。

経営者目線ですが、業務の標準化にも繋がるのです。
「普通」とか「当たり前」って人によって違うんですよね。
そのようなブレをなくすための「証拠」になるんです。
僕自身経験があります。あれは運動会練習を合同で行ったとき。あっちの園長先生に言われて変えたらこっちの園長先生に怒られて…「えーーーーーー!!!そんなーーーー!!!」と、心から思いました。
管理する側にこそ必要
現場の先生にも勿論必要なのですが、管理職の先生にもとっても重要なのです。
マニュアルは、管理職が現場を把握する為にも存在するのです。
みんなで同じことをやって可否をチェックする為の、マニュアルはこの叩き台なのですね。

マニュアルがないと、現場でなにやってるのかわかんなくなっちゃうんですね。管理職としては、それは非常にまずいです。
管理職の仕事は業務の効率化。質を上げることも含まれます。
管理者が実際に現場に毎日入ることは難しいので、みんなが見てわかりやすいマニュアルを作るしかないんです。

確かに、管理職の方にしかできないことかもしれませんね…
新人・転職者の強い味方になる
教わった方もわからなくなっちゃった時に、個人で確認できるのはありがたいですね。

この前教えてもらったんだけど、えっと、どうするんだっけ?もう一回確認したいんだけど、同じ事聞いちゃうと怒られるかも…
ですので、新しく来た先生に教える際はマニュアルと照らし合わせながら教えると、かなり効率的です。
予習してからの実践ができるのです!

それでも「わかりづらい!」となった場合、更なる更新のキッカケにもなります。
きちんとしたマニュアルがあれば「内定辞退者減る」というデータもあります。マニュアルを面接のときに見せると安心するようで、数字が明確に出ています。
どんなマニュアルを作ればいい?
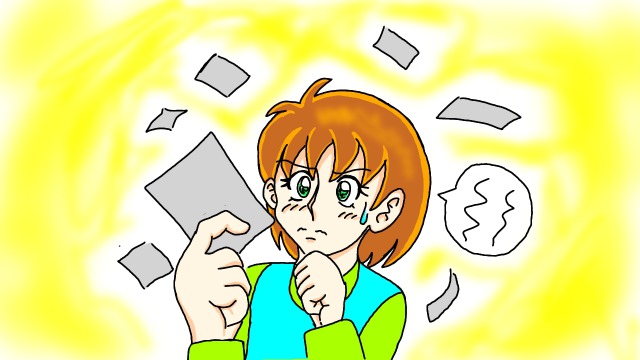
写真を使ってわかりやすく
文章だけでは限界があります。
もちろん場合にもよりますが、写真を使って作成することをオススメします。
そして文字だらけになると、読み飛ばされてしまう可能性が出てくるので、文字はなるべく少なくするよう心掛けています。
僕は写真に「吹き出し」を使ってわかりやすくするようにしています。

確かに、新聞みたいなマニュアルだと読む気すら起きないかもしれませんね…
動画も必要だけど、基本は紙で
動画だと、いざ実践する際に、見ながら行うのは難しいですよね。
特に運動会・御遊戯会等の「大きな行事」はマニュアル化必須と思います。
その方が流れがわかりやすいからです。後から見返していろいろと気付くことが出来ます。
- 何時から始まったか
- 園児の入場はどんな感じか
- 周りの状況を見て気を付けることはないか
それを見て紙にまとめます。
それを配布し、それを見ながら動画を見ることでより効率化です。

大きな行事等では、僕は台本を作ったりします。
マニュアル作成は管理職の仕事
きちんと文書として残しておかないと反省会をしても…
- その年だけの反省になってしまう…
- 先生個人のノートに書かれたきりに…
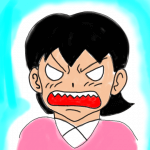
なんで×年も乳児クラスやってるのにわかんないの!!
なんて怒っても意味がありません。
全て管理側の責任です。
毎年同じまちがいが怒るのは管理側の責任
事例:運動会
例えば運動会準備…
- 入退場門のどちら側に整列するか?
- 笛を吹くタイミングは?
- 音響への合図は誰がどう送るか?
- 開会式に必要なものは?
- 園児席や荷物置きの設置方法は?
- そもそも必要なモノは?
これらを全て口伝えでやるのは大変ですし、解釈の違いが生まれるのは必然です。

あれ?去年もそんな感じでしたっけ?

うそ!違ったっけ?いつもどうしてるっけ?
このような行き違いが起きる可能性が高いです。
まとめ
今回は「保育園のマニュアル」について書かせていただきました。
マニュアルは先生方や、新人、転職者、管理職のみんなに必要なものなんですね。
オススメ書籍
この本は「全ての管理職に読んで欲しい!」と思います。マニュアルの大切さが非常にわかりやすく書いてあります。

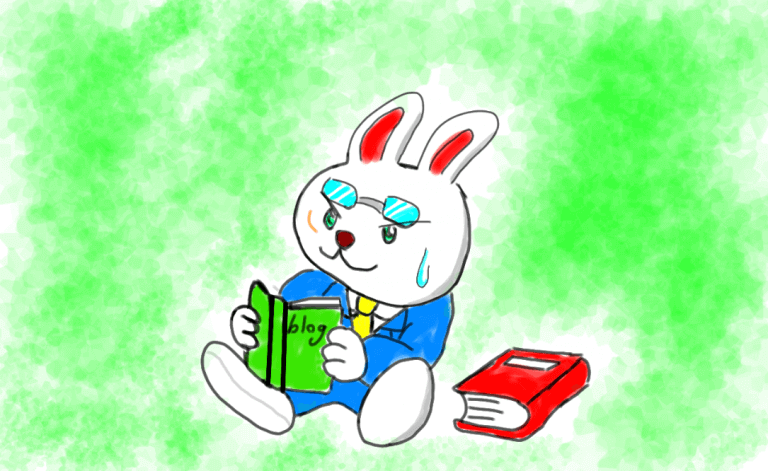



コメント