
こんにちは!ともや先生です!
下の子が生まれたら、上の子にはなにが起こるのでしょうか?
僕にも上の子が三歳半のときに下の子ができました
僕も含め、親が下の子にかまおうとすると、それを阻止しようと下の子を叩こうとするのです
これには本当に困りました…
しかし、そもそもなぜ上の子は下の子を叩いてしまうのでしょうか?
それについての原因と対応法をわかりやすくまとめました
そして僕が実際に我が子にどう対応したかも合わせて、お話していきたいと思います
なんで下の子を叩くのか?

自分を必死で守っている
実は、下の子を叩くことによって、自分を必死で守っているのです
具体的に、どんな状況で叩こうとするのか?
代表的な例でいえばこんなところでしょうか?↓
- 名前を呼ぶ
- 話しかける
- 抱っこする
- 絵本を読む
- ミルクをあげる
困ってしまいますよね?そこで思う事はこんなこと…

なんで叩いてくるの?叩くなら私を叩けばいいのに、なんで赤ちゃんを叩くんだろう・・・
そんな風に思ってしまうかもしれませんが、上の子の気持ちを考えてみて下さい
当然ですが、生まれたばかりの赤ちゃんはなにもできないので、お世話をするのに大人はかかりきりになってしまいます
それを、上の子からしたら「下の子に全てをとられた!」と感じてしまうのです
今まで全てが自分優先だったところ、下に赤ちゃんが生まれた為、今までする必要がなかった我慢をすることになったとしたら…納得いかないのも無理はないかもしれません

どうしても下の子に合わせなくてはならない時ありますよね…
大人は理解していますが、上の子からしたら、突然現れた赤ちゃん!戸惑うのも当たり前です
もっと言ってしまうと、突然現れた赤ちゃんは侵略者なわけです

例えるのなら、とられたオモチャを取り返しにいっている感覚です
叩くという行動で「パパ、ママを返せ!」と言っているのですね

「自分はもしかしたら愛されていないんじゃないか?」とっても不安なのですね…想像すると、ちょっと切ないです…
怒るのは逆効果
ここで気を付けたいのは、下の子を叩いたからといって、感情に任せて怒るのは逆効果であるということです
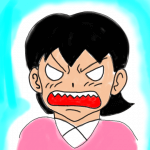
なんてコトするの!!叩いちゃダメでしょ!!何度言えばわかるの!!
気持ちはわかる気もしますが、上の子からしたら…

アイツのせいで僕は怒られてるんだ・・・チクショウ!僕はなにも悪くないのに!!
そういう風に解釈され、行動がますますエスカレートしてしまう恐れがあります

パパやママをとられた!と思っている上に、怒られてしまっては、子どもの気持ちは行き場を失います…
理不尽な思いをした!という気持ちだけが残るだけの場合があるので、怒る前に、ちょっと踏みとどまって考えてみることが必要です
僕がやった6つの対応

実際に叩いてしまった時はどうすればいいのでしょうか?
うちの子も、下の子が生まれた事で、つい下の子を叩いてしまうことがありました。
僕が実際に行ったことをお話しします。
①叩くことはなぜいけないか説明する
上の子が下の子を叩いてしまった場合、怒るよりは落ち着いて説明しましょう。
現場を見て頭ごなしに怒ってしまうと、子どもも大泣きパニック状態。それではどんな話も通じません。
そして、あくまで「叩くという行為そのものがいけない」という事を伝えて下さい
繰り返しますが「行為」そのものについてお話しして下さい
その際に、必要以上に大きな声を出したり「前も言ったよね?」等過去の事を持ち出したり「なんでそんなに乱暴なの?」等人格否定をするのは避けたいところです

叩くのは痛いからやめようね
どうして叩きたくなっちゃったの?
パパは痛いのは嫌だな
実際に僕もそのように対応しています

責めるような口調はNGです
冷静に!落ち着いて対応しましょう
その際に子どもを否定して考えを変えさせようとするのはやめて下さい…さらに溝が深まります…
例えば、説明しているのに

叩いてもいいんだよー!

だからダメだって言ってんだろー!
と怒ってしまうと、これでは話になりません
大事なのは繰り返し説明することです

叩いてもいいんだよー!
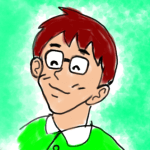
そうなんだ
でもパパは叩くのは嫌だな…だって痛いもん
これくらいでいいと思います(繰り返しますが否定はNGです)
3歳以上になると、子どもも自分で考える力が備わってくるので、自分で考えます
その時はまだわからなかったとしても、繰り返し伝え続ければ必ず届きます

実際にウチの家庭でも、2、3ヶ月ほどで叩くことはなくなりました
②プラスの言葉に言い換える
叩くことはいけないと説明した後にして欲しいのはコレ
3歳頃ですと、上の子は下の子に抱いている感情がなんなのかよくわからないのです
親がポジティブな言葉に置き換えて伝えてあげたいところです
例えば…↓
- 本当は遊んであげたかったんだよね?
- お世話してあげたかったんだよね?
- 頭なでなでしてあげたかったんだよね?
- 本当は大好きなんだよね!
これも大切なのは繰り返し伝える事
僕は実際に…

本当はいい子いい子したかったんだよね?これくらいの力でたくさんいい子いい子してあげてね
と言い、実際に上の子の頭を撫でました
実際にやってみせる事で、言葉よりも伝わりやすく、触れ合うことで上の子の心も満たされます
③愛情を与える
前述しましたが、上の子は下の子が生まれたことにより「自分が愛されていないのではないか?」と不安に感じているのです
不安を感じさせないように愛情を注いであげて下さい。
僕は実際にスキンシップを多くとったり「大好きだよ!」と言葉で愛情を伝えています。

まぁ純粋に我が子が好きすぎて普段から行っていることなのですが…
そして、僕が個人的にも、最もして欲しい事は、寝かしつけです。
僕もなんとか子どもの寝かしつけまでには家に帰るようにしています。
忙しい時も、なんとか仕事を片付けて、いそいで家に帰って、とりあえず風呂だけでも入って、子どもと一緒に寝ています。そして、その日あった出来事を話しながら一緒に布団に入ります。
日中なにかあったとしても、心が満たされながらその日が終わることができたのならば、きっといい夢が見られることでしょう。
一緒に寝る。というのは非常に大切なコミュニケーションなのです。
できれば、普段忙しいお父さんも参加したいところです。

毎日は無理だとしても、できるだけやってあげたいですね。他には「一緒にお風呂に入る。」ということも非情に大切です。忙しいお父さんも、土日だけでもいいのでやってみてはどうでしょうか?
④お世話をする事に巻き込む
- 泣いてる!どうしたらいい?
- ほら!抱っこしてあげて!
- 助けて!困ってるんだ!
これは僕もよくやっていたのですが、下の子が泣いて、すぐに抱っこしようとすると怒ることがあるので、

大変!泣いてるよ!抱っこしてあげて!
と、巻き込んでしまいます。
実際に息子にやてみたところ「わかった!」と言って少し抱っこしてもらって(勿論危なくないように親が支えます。)5秒くらいやったら飽きたのか?別の事をやりに行ってしまいました。
オムツを変えようとしても怒ることがあるので「大変!オムツ出てるよ!変えてあげて!お願い!」と巻き込んでしまいますしまいます。当然「できない!」となるので、「じゃあパパがやるね。」と交代します。
役割を与えるのもいいです。
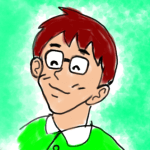
じゃあ、新しいオムツ持ってきて!わー、ありがとう!助かるなぁ!
一緒にお世話をしているという感覚を共有できると、お兄さん、お姉さんであるという自覚も芽生えてきます。
そうなれば、叩いてしまうことも少なくなっていきます。
⑤あえて甘えさせる
親の気を引きたくて、普段からできていることもやってもらいたがることがあります。
一人で着替えられるのに、「やって!」と言ってきたりします。
可能な限り応えてあげて下さい。

できなーい!やってー!
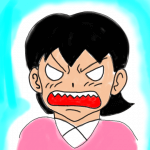
甘えるんじゃないの!自分でできるんだからやりなさい!
忙しくて余裕がないときに、ついつい言ってしまうこと、あるかもしれません。
ここで突き放してしまうのではなく、やってあげましょう。
子どもは不安なのです。愛を試されているときなんですね!
なのでそのような場合は
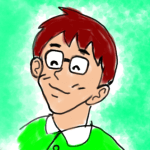
いいよ!でも、次からは自分でできるようになるといいね
これだけで大丈夫です。
そこで、「そうするとわがままに育つのではないか?」という疑問が出てくるかもしれません。
例えば、言われるがままにお菓子を与える。言われるままにYouTubeを見せ続ける。等はそうですが、着替えさせて。食べさせて。お靴履かせて。くらいは問題ないと思います。
もともとある家庭のルールは変えず、毅然とした態度で向き合いましょう。

毎回やってあげてたら、なんにも一人でできない子になるんじゃないの?

そのうち勝手に自分でやるようになるので、心配いりません。
その時はやってあげたとしても、次はなにも言わなくても勝手に服を着ていたりすることもあります。そんなもんです。
⑥「仲良しが嬉しい!」と言葉で伝える
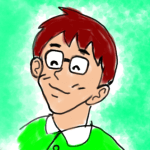
〇〇と△△が仲良くしてくれてると、パパも嬉しいな!
親がきちんと言葉で伝える必要があります。
子どもからしたら…

え、妹と仲良くしてるとパパやママも嬉しいんだー!知らなかった―!
という具合に、純粋に知らない!という場合もありえます。
僕も実際に自分の息子に…

〇〇と遊んでくれてるんだ!ありがとうね!
仲良くしているのをみると、パパも嬉しいなぁ…!
こういう風に言うと、けっこうはりきって積極的に遊んでくれたりします。
絵本を読んでくれたり、一緒にパズルをしたりと…
微笑ましいですね!
まとめ

下の子が誕生した今!そう、今こそ親の愛情が試されているんです!!
上の子は「本当に自分は愛されているか?弟や妹ができても自分に対する愛情は変わらないのか?」不安で不安でしょうがないんです。
まだ自分の気持ちを上手に言葉で表現できないので、行動に表すのです。
どうか、子どもの心に「安心」を与えてあげて下さい。

僕は「赤ちゃん返り」という言葉が不適切であるように感じているのです。なにか、子どもを軽く見ているような、そんな言葉で片付けないでほしい。感じがするんです。





コメント