
こんにちは!ともや先生です!
保育所保育指針は皆様読んだことありますか?
最近では2018年3月に改訂されました。
今回は誰にでもわかりやすく解説していこうと思います。
皆さん「保育所保育指針」読んだことありますか?僕も最初の頃に挑戦しましたが、すぐに眠くなり挫折…
なので、誰にでもわかりやすく、理解出来るような内容にしたつもりです。
保育所保育指針は、序章と1~5章にまとめられていて、本記事は「序章」についてまとめてあります。
※本当は今回で全ての章をまとめようかな、とも思ったのですが、そんなことしたらとんでもなく長くなるので…
保育指針は読まないとダメなのか?

え?指針なんて読んだことないよ!そんなん本当に役に立つの?なんて思いませんか?
大丈夫です。わかりやすく解説していきますよ!
読まなくても保育はできる
結論から言うと、指針は読まなくても保育士にはなれます。

ゲームの説明書を読まなくても、感覚でなんとかなっちゃったりするものですよね。
というのも、書き方が難しいんです。
難しい漢字ばっかりで、生まれて初めて聞くような言葉、言い回しもあり「あえて難しく書いているのかな?」なんて思ってしまったり…

実際に僕の周りでも指針を読んだことのない保育士さん、けっこういます。
それでも、読んで欲しい理由が指針にはあります。
それでも読んだ方がいい理由
読まなくても保育士できるのに読まなきゃダメ?なんて思うかもしれません。
ですが、読んだことがない人が改めて読んでみると…「え、そうだったの!?」ということに気が付けると思います。

ゲームの説明書でも、改めて読んでみると「このボタンでこんなことできたの!?知らなかったわー!」ということありませんか?
そして、保育士とはどんな仕事なのか?本当に基本的なことが書かれています。
保育士という仕事を、きちんと理解してやっているのと、ただなんとなくやっているのとでは、そこに差が出てくるのは当然と言えます。
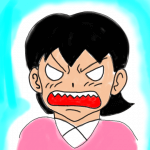
なんとなくで保育士やってんじゃねーよ!
なんて怒られたくないですね…

確かにスポーツのトレーニングとかでも意味をわかっているかどうかで、質も意識も変わってきそうです。
そして世間一般、周りからは「保育士である以上指針の内容は十分に理解している」ということが前提で見られることも少なくはありません。
1 保育所保育指針とは何か?

一番最初に「保育所保育指針って、まずなんなの?」ということを記してあります。
なんなんですかね?
一番大切なこと:子どものため!
まず一番大切なことをお伝えします。
保育所という存在は「全ての子どもの最善の利益のため!保育所は子どものためにありますよ!」という事が冒頭に書いてあります。
親じゃないんです、先生でもないんです。全ては、将来この国をしょって立つ子ども達の為なんです!
そんなの当たり前じゃん!なんて思うかも知れませんが、そうなんです!

当たり前なことこそが一番大切なんです。今一度心に刻んでおいて下さいね!
保育士としての「証拠・根拠」になる
保育士としての「証拠」や「根拠」になることが書いてあります!
例えば先輩から…
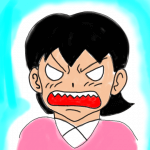
「教育」は保育士の仕事じゃないから!

指針には「養護及び教育を一体的に~」って書いてありますー!
先輩に言うにはなかなか勇気いるかもしれませんが、こんな事も言えてしまうワケなんです。
なので、皆さんも指針を正しく理解していれば、保育でなにか困ったことや、相手と衝突した際に「指針にこう書いてあるから!」と証拠・根拠を示すことができるのです!
そんな事言われたら相手はもうなにも言えません。動かぬ証拠。というやつですかね。

水戸黄門の印籠みたいなものですかね?指針を否定したら保育士なんてやってられません。
保育はみんなで協力して行っていくもの
そして「保育園の先生達みんなで協力しあって、みんなで考えて保育を実行しようね!」と書いてあります。
そう、保育というものはチームプレイなんです。

人がひとりでできることなんて、たかが知れていますからね。
2 保育所保育指針の基本的な考え方

厚生労働大臣が作ったもの

ここでまず「厚生労働大臣ってなに?」と聞かれてうまく説明できますか?
保育所保育指針というものは「厚生労働大臣が、みんなこれ絶対知っといてね!」という思いで作ったものです。

え?なんか偉い人でしょ?政治家?内閣総理大臣みたいなもんでしょ?
はい、まずはそこから説明します。
国務大臣の一つで、厚生労働省で一番エラい人のことです。はい、まだよくわからないですよね?
厚生労働省とは、日本に住んでる人達が、元気で安心して暮らすためにお手伝いをする団体のことです。
具体的に言うと…
- 病気の予防
- 食べ物の安全
- お仕事の紹介
等があげられます
このように、皆様の幸せを願っている厚生労働省が「こんな保育園にしてあげてね!」という願いが込められて、書いてあるものなのです。
書いてあることは3つにわけられる
そして、この指針に書いてあることは
- 絶対に守らなくちゃいけないこと!
- 今はできてなくてもいいんだけど、頑張って実現させて!
- 一応こうなってるけど、その保育園のやり方にあわせてやってみてね!
ということの3つにわけられていて、これを元に「保育の質を上げていってね!」としています。

なるほど!「保育の質」を上げる為にもとっても大切なんですね!
「全ての子どもたちの為に作ったから!日常的に使って下さいね!」という願いも込められています。

日常的に!?う~ん…これは確かに「読んだことないや…」なんて言ってられないかもしれません…
3 どうして改訂したのか?
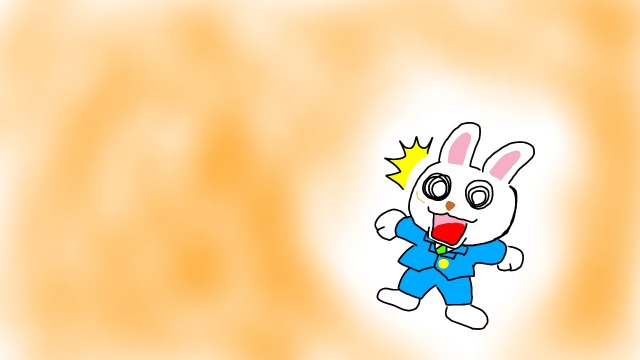
保育所保育指針は1965年に作られました。調べてみたら、あのオロナミンCが初めて発売された年だそうです。
そして4回改訂されています。一番新しい改定は2018年H29です。
なぜこんなに改訂されてきたか?それは時代が変わったからです。
1つひとつ説明していきましょう!
①日本はどんどん子どもが減っている国だから
日本も昔はガンガン子どもが増えている時代もあったんです。
ですが今の時代、赤ちゃんが生まれる数が年々減っていく傾向があります。

また赤ちゃんが増えるときがあるんですかね?

その時はまた時代も変わっていて指針もまた改定されるかもしれませんね。
2016年、ついに出生率は百万人を割ってしまいました。これはかなり大きい変化です。
多い時は、年間の出生率が250万人とかいたので、それと比べると半分よりも、かなり下回っていますね。
②大家族が減ったから
日本は核家族が増えてきています。
※核家族とは、パパとママ、その子ども達で暮らす家庭の事。

例えるなら「クレヨンしんちゃん」みたいな家庭のことです。
それって普通じゃない?なんて思ったりしませんか?
昔では、同じ家におじいちゃんおばあちゃんと息子夫婦、その孫といった3世代で住む「大家族」が多かったそうです。

例えると「サザエさん・まる子ちゃん」みたいな家庭ってことですね。
それが、時代とともに少なくなってきています。
③ご近所付き合いが減ってきた
昔は町全体で子育てをしている事がありました。
イメージとしては以下のような感じです↓
- オールウェイズ三丁目の夕日
- クレヨンしんちゃん大人帝国の逆襲
- こち亀の両さんの少年時代
商店街のお店の人はみんなよく知るおじちゃんおばちゃんで、近所の人みんな顔見知りだったんです。

今はショッピングモールが主流で、商店街はシャッター閉まっているお店が多いですよね…
今はマンションでも隣に誰が住んでるか顔も知らなかったりしませんか?たまーにすれ違う時に軽く挨拶することの方が多くないですか?

近所のおばちゃんに気軽に相談したり、預けたりも今はしないですよね…
地域との関わりが、昔と比べて薄くなってきているのです。

それが子育てが「孤育て」と呼ばれる理由の1つにもなっています。
④共働き家庭が増えたから
昔は今と比べて専業主婦が多かったんです。

確かに「サザエさん・クレヨンしんちゃん・ドラえもん・もちびまる子ちゃん」も、国民的アニメの家庭はみんなお母さんは専業主婦です。
それが今!日本は働く女性が増えています。

女性の社会進出!ですかね?海外では女性大統領もいます。
時代の変化。ご理解いただけたでしょうか?

あの「しまじろう」のお母さんも、昔は専業主婦だったのに、時代に合わせて今は仕事をしています。因みに絵本作りです。ライターというやつですね。
子どもの数が減ってきて、おじいちゃんおばあちゃんとも別に暮らして、地域との関わりも薄くなり、共働きが増えた。つまり、人との関わりが減ってきているということなのです。
そして乳幼児期の大人の関わりが非常に大切!ということも様々な研究で明らかになってきました。
なので、より一層!保育園の役割ってとっても重要なんですよ。ということに繋がるのです。

「保育指針も時代にあわせて変えていくから!ちゃんと使ってね!」ということが書かれています。
4 改訂の方向性
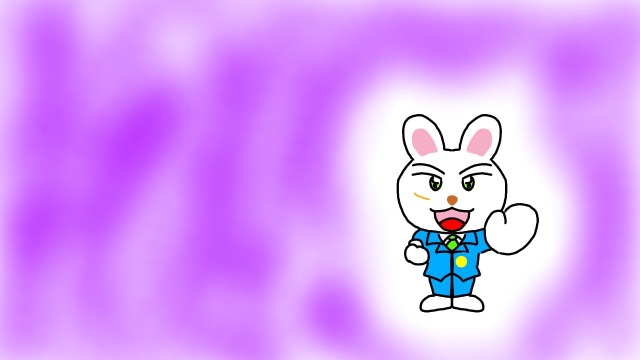
ではどういったことを改定したのかの説明に入ります。
①0~2歳児の部分を詳しく追加
指針には「乳児・1歳児以上3歳児未満の保育に関する記載の充実」とあります。
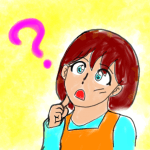
乳児・1歳以上3歳未満児…というと、つまり…?
要するに、「0歳児クラス~2歳児クラスの事を、もっと詳しく書き足したよ!」ということです。

その期間が非常に大事!「子どもの一生の学びの出発点となる!」と、いろんな研究で示されていますよね。
※厳密に言えば、2歳児クラスで3歳になった子は除外されます。
「児童福祉法」に拠ると「乳児とは、0歳の赤ちゃんのこと」で、1歳になったら、もう乳児は卒業で、1歳~小学校に入るまでは「幼児」という扱いです。
そして、詳しく追加された内容こそが「5領域」に繋がる、前の段階「3つの視点」というものなのです。
※「3つの視点」や「5領域」については、また別記事で解説します。
②「幼稚園・子ども園」との違いを少なく
保育園に「保育所保育指針」があるように…
子ども園には「教育・保育要領」
幼稚園には「幼稚園教育要領」
というものがあります。
詳しい管轄は以下の通り↓
- 保育園は厚生労働省
- 幼稚園は文部科学省
- 子ども園は内閣府

それぞれ「子どもに関わる施設」という部分は一緒ですが、管轄が違うんですね…
それら同士で「言ってる事の違いを少なくしようよ!」としたのが今回の改訂です。
そして、具体的に子ども達にどうなって欲しいか?どういった状態で小学校に送り出したいか?というものを「幼児期の終りまでに育って欲しい姿」として明確に記しました。

「幼児期の終りまでに育って欲しい姿」は10項目にわかれています。1章の4で詳しく解説しますが、これこそが今回の改定の目玉!とも言える部分ですよ!
③時代にあわせて「やり方」を変えていこう
今の時代、ものすごい早さで世界は変わっています。※時代の移り変わりについては上記した通りです。
その中でも「子ども達の環境・安心・安全・健康」について、時代に合わせてやり方を変えていきましょうね!
という思いのもと、見直された部分になっております。
例えば「安全」です。
「311」と言われる大地震が、いつ起きても大丈夫なように準備しておいて下さい。みんなで協力して備えておいて下さい。
という部分。
例えば「環境」です。
幼児期の関わりが非情に大切!ということも上記の通り研究で明らかにされてきましたし、配置基準の見直しなんかもそうです。時代に合わせて保育もやり方を変えていきましょう!
という部分も見直されています。

時代が進むと「AIとの付き合い方!」という項目も追加されていくかもしれませんね!
④悩める保護者を助けてあげて!
保育園の保護者支援が、より重要になってきています。

保護者支援とは「保護者の育児についての相談に乗ったりして、一緒に子育てを楽しんでいきましょう!」ということです。
上記もしましたが、昔は町全体で子どもを見守っていることもありましたが、今の時代地域との繋がりは薄くなってきています。
その為、育児について相談できずに一人で抱え込んでしまっている人も年々増加傾向に…

共働きより専業主婦の方が鬱になりやすいって聞いたことあります…
そこで、保育所は保護者と地域の人々と協力をして、その子ども達の事を支えてあげて下さいね!と記されています。

今までは「保護者に対する支援」だったのですが、今回の改訂で「子育て支援」に変わりましたね。
⑤保育士のスキルアップ!
保育士さんは昔と比べてやることが増えて、難しくなってきています。
そこで、保育士としてのスキルアップが求められています。

保育士って「なんでも屋さん」なんて言われたりしますよね…
代表的なところでいうと、上記の保護者支援、不適切保育について、幼児期の終りまでに育って欲しい姿等…
その為に「研修を行う事が大切!」とされています。
この場合の研修とは園内研修や外部研修の両方です。
園長中心になって、研修を計画的に行って下さいね!と。書かれています。
そして「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」が定められました。

保育の質を上げていくためにも欠かせませんね!
これからはこのガイドラインに基づいて外部研修をしていって下さいね!とされています。
5 改訂の要点
以下の5つについて改定されております。
- 総則
- 保育の内容
- 健康及び安全
- 子育て支援
- 職員の資質向上

以上の5点はそのまま指針の目次にもなっていますね!
そして、今までの指針の内容も大切にしながら、時代や最新の研究結果をもとに、見直したり付け加えていこう!ということが書かれております。

保育の世界も時代とともにどんどん変わってきています!
まとめ

今回は保育指針の「序章」についてお話させていただきました。
なるべくわかりやすい解説を心掛けたのですがどうでしょうか?
これから先、1~5章まであるので順番に解説していきたいと思います!
序章で示した事を次回からどんどん掘り下げていってみようと思います!もしよければ覗いてみて下さい!
※1章を解説したらここにアップします。



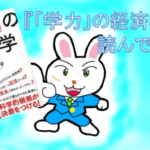
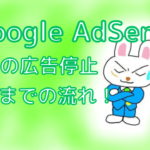
コメント